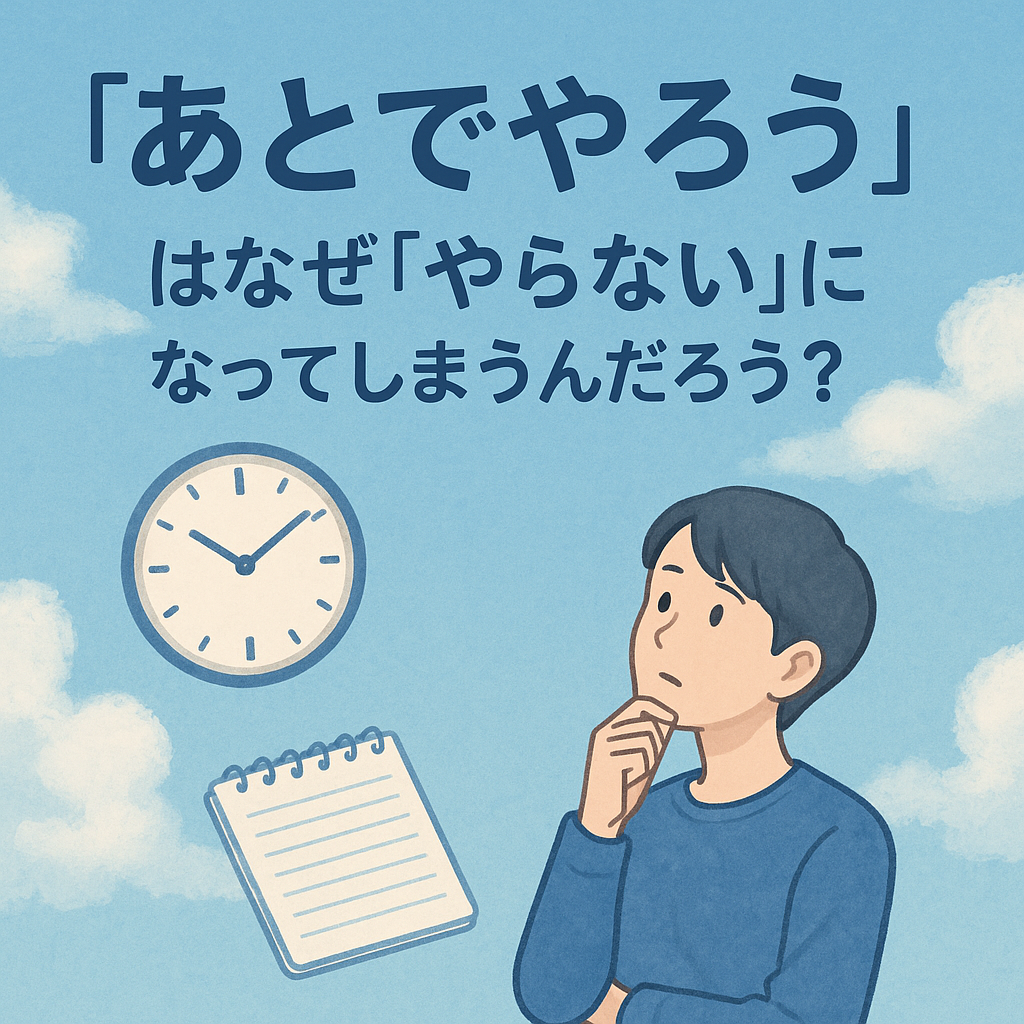「あとでやろう。」
誰もが一度は、いや何度も口にしたことがある言葉ではないでしょうか。
掃除、返信、資料づくり、買い物リスト、メモの整理…。今やらなくてもいいこと、今はやりたくないこと、あるいは今できないことに対して、私たちはよく「あとでやろう」とつぶやきます。
けれど、不思議なことにその「あとで」は、たいていやってこない。
ふと気づけば数日経っていたり、思い出すことすらなくなっていたり。
まるで「あとでやろう」と思った瞬間に、それが「やらない」の方へ静かに傾いていくような感覚があります。
この記事では、「あとでやろう」がなぜ「やらない」に変わってしまうのかという心理的な流れと、それでも自分を責めすぎずに、できることを見つけていくための小さなヒントをお届けします。
なぜ「あとでやろう」と思ったことは後回しになるのか
「あとでやろう」と思ったことが、なぜか実行されないまま日が過ぎていく──。
この現象には、私たちの脳と心のはたらきが関係しています。
そもそも「あとでやろう」と思うとき、私たちは“未来の自分”にその仕事を委ねています。
「今は忙しいけど、あとでならできるはず」「今は気分が乗らないけど、あとならやれるだろう」と、どこかで“あとでの自分”の方が優秀でやる気があると信じているのです。
ところが現実には、あとでの自分も同じ自分です。時間が経っただけで、急にやる気が湧いてきたり、気持ちが整ったりするとは限りません。むしろ、あとでになればなるほど、面倒に感じたり、気が重くなったりして、さらに行動から遠ざかってしまうのです。
また、脳は「先延ばしにすることでストレスを回避できた」と錯覚する性質もあります。
ほんの一瞬「あとでやろう」と決めたことで、今そのことから解放された気分になり、実行そのものへの意識が薄れていく。そのまま忘れ去られる、という流れになりがちなのです。
「あとでやろう」は“今はやりたくない”の別の言い方?
「あとでやろう」と言うとき、私たちは本当に“あとでやる”つもりなのでしょうか?
もちろん、そのつもりで言っている人もいるでしょう。ですが実際には、その言葉の裏にあるのは「今はやりたくない」という本音であることがほとんどです。
たとえば、
-
気分が乗らない
-
めんどうくさい
-
頭が疲れている
-
他に気がかりがある
そんなときに、「今はできない」と素直に言うのではなく、代わりにやる意思はあるように見える“あとでやる”という言葉を選んでいるのです。
この言葉には、「今は逃げたい」「でも完全にやめたとは言いたくない」という、心の中の葛藤をやわらかく包む役割があります。
ある意味では、自分を守るための防御反応ともいえます。
しかしこの“やるかもしれない”という曖昧な約束は、時間が経つほど曖昧さを増していきます。やがて「やる気が起きたらやる」に変わり、気づけば“やらないまま忘れる”という結末に。
「あとでやろう」という言葉は、やらないことにしたいけど、罪悪感を感じたくないときの便利な逃げ道でもあるのです。
だからこそ、もし自分が何かを「あとでやろう」と思ったときは、「今、やりたくない理由は何か?」と立ち止まってみることが、自分と上手につきあう第一歩かもしれません。
“やる気”は「あとで」より「今」に宿る仕組み
「今はやる気がないけど、あとでならできるかも。」
そう思って何かを先延ばしにすること、誰しも経験があるのではないでしょうか。
けれど実は、“あとで”になったからといって、やる気が自然に湧いてくるとは限りません。
むしろ、「やる気」は“今、動いた人”のところにやってくるのが本当のところなのです。
やる気は「行動のあと」にやってくる
心理学では「作業興奮(さぎょうこうふん)」という言葉があります。
これは、面倒だと思っていたことでも、やり始めると自然と集中できてくる状態を指します。
つまり、やる気というのは「やるから出る」ものであって、「やる気があるからやる」わけではないのです。
たとえば、
-
とりあえず5分だけ掃除を始めたら、気がついたら30分経っていた
-
メールの1通目に返信したら、ついでに全部返していた
そんな経験がある方も多いのではないでしょうか?
“あとでやろう”は行動を止める合言葉
一方で「あとでやろう」は、ある意味で“今、動かない理由”を自分に与える言葉です。
「まだやらなくていい」「今じゃなくてもいい」と自分に言い聞かせてしまうと、脳も体も“休むモード”に切り替わってしまうのです。
そのまま時間だけが過ぎていき、やる気はやってこないまま…という悪循環に陥ることも。
“やる気待ち”より“小さく始める”がカギ
本当にやるべきことがあるときは、「あとでやろう」と思う前に、まず1分だけ手をつけてみることがおすすめです。
-
メモ帳を開くだけ
-
テーブルを一か所だけ拭く
-
タイトルだけ書いてみる
そんな小さなスタートでも、「動き出した自分」にやる気は反応してくれるのです。
「あとで」がうまくいく人といかない人の差
「あとでやろう」と思っても、実際にあとでちゃんとやる人と、気づけば忘れてしまう人がいます。
この差は何なのでしょうか?
単なる性格の違いだけではなく、“あとで”の扱い方や意識の向け方に差があるのです。
「あとで」をスケジュール化できる人
“あとで”を成功させる人は、感覚ではなく「時間」で管理しています。
-
「午後3時にやる」と決めてカレンダーに入れる
-
タスクアプリでリマインドをかける
-
手帳に「〇〇をやる」とメモしておく
つまり、「あとでやる」を“行動として予定に組み込む”ことで、頭の中だけで終わらせない工夫をしています。
「あとで」がぼんやりしている人は忘れやすい
一方で、「あとでやろう(けど時間は未定)」という状態では、記憶の中でそのタスクがぼやけていきます。
そして別のことに意識が向いた瞬間に、その“あとで”はどこかへ消えてしまいます。
さらに、時間が経つほど「やってないこと」への罪悪感が生まれ、無意識に遠ざけてしまうという心理も働きやすくなります。
“あとで”を使うなら、自分の癖を知っておこう
「あとで」がうまくいかないタイプの人は、自分にとって“あとで”という言葉が実質「やらない宣言」になっていることを理解しておくと、行動が変わりやすくなります。
-
あとで=忘れるなら、今ちょっとだけやる
-
あとで=不安になるなら、リマインドで管理する
-
あとで=気が重くなるなら、小さく分けておく
このように、「あとで」を過信せず、“現実に落とし込む”意識があるかどうかが、成功と失敗の分かれ道になるのです。
それでも「あとでやろう」と思ったときに、できること
「あとでやろう」と思うこと自体は、悪いことではありません。
むしろ、それが適切なタイミングであれば、今やるよりも効率的だったり、気持ちが整った状態で取り組めることもあります。
大切なのは、「あとで」が“やらない”に変わらないように、自分の行動をサポートするしくみを持っておくことです。
「あとで」の内容を“見える化”する
「あとでやる」を頭の中だけで留めず、メモやリマインダーなどに“外だし”することで、忘却を防げます。
-
スマホに通知を入れる
-
手帳や付箋に「あとでやること」を書く
-
音声メモで録音しておく(5秒でもOK)
こうすることで、あとでの自分が“気づける状態”を作れます。
「あとで」のタイミングを決めておく
「午後になったら」「夕食後に」「寝る前に」など、具体的な時間や状況を決めておくことで実行率が高まります。
「いつか」ではなく、「このとき」と決めておくことで、心の準備もでき、行動につながりやすくなります。
それでもできなかったときは、自分を責めない
忘れてしまうこと、やる気が出ないこともあります。
そんなときに「またできなかった」と責めると、自己否定につながってしまい、次の行動への意欲まで下がってしまうのが人間です。
それよりも、「やらなかった理由」を静かに見つめてみたり、「やらなかったこと」に意味を見出す方が、長い目で見て前向きです。
「今日は疲れてたんだな」
「あれは本当はやらなくてもよかったのかも」
そんなふうに、“あとで”をきっかけに、自分とやさしく向き合えるようになれたら、それだけでも価値があるのかもしれません。
まとめ
「あとでやろう」。
それは、自分に少しだけ余裕を与える魔法のような言葉ですが、時にその魔法が“やらない理由”へとすり替わってしまうこともあります。
「あとで」は未来への前向きな約束のように見えて、実は「今やりたくない」のやさしい言い換えだったりします。
そして、やる気というのは「あとで湧く」のではなく、「今動き始めた人」にこそ宿るものです。
でも、「あとでやろう」と思った自分を否定する必要はありません。
大切なのは、その“あとで”が本当に来るように、小さなしくみや習慣を添えてあげること。
そして、もしできなかったとしても、「できなかった理由に目を向けること」が、次の一歩につながっていきます。
“あとでやろう”を責めるのではなく、
“あとで”の自分にやさしく寄り添うような時間を持てたら――
それはそれで、ちょっといい「そら色じかん」になるのかもしれませんね。