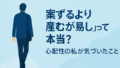「確かにこうだったはず」が間違ってた
たとえば、家の鍵。
「ここに置いたはず!」と決めつけて探し続けた結果、まったく違う場所から見つかった、なんてことありませんか?
私自身、日常の中でこうした“勘違い”に何度も振り回されてきました。
・スーパーで「醤油はまだある」と思い込み、料理中に空っぽと気づく
・「USBメモリを持った」と信じて会議に向かい、鞄の中に見つからず大慌て
・「あの人に伝えたつもり」が、実は伝えていなかったという誤解
どれも大きな失敗ではないけれど、地味にストレスになります。
しかもこうした思い込みに気づくのは、たいてい「もう遅い」ときなんですよね。
思い込みの正体は「自分だけの前提」
思い込みの厄介なところは、それが「自分の中では完全に正しい」と信じてしまっている点です。
たとえば、
「これは常識だから、みんな知ってるはず」
「言わなくてもわかるでしょ」
「きっとこうに違いない」
…こうした“勝手な前提”が無意識に行動に影響を与えているのです。
実際に他人と話していても、自分の思っている常識が相手には通じないことがあります。
その瞬間、「あ、自分の基準で考えてたな」と気づかされます。
つまり、思い込みは「自分の経験や記憶から作られた、自分だけの地図」なんですね。
思い込みが生まれる理由と脳の仕組み
人間の脳は、繰り返し使う情報を“パターン化”して処理する仕組みを持っています。
毎回ゼロから判断していては疲れてしまうため、「たぶんこうだろう」「いつも通りだろう」という省エネ思考になるのです。
この仕組み自体は悪いものではありません。
むしろ、私たちが効率よく生活するためには必要な能力です。
ただ、その「慣れ」や「記憶」が間違っていたとき、ミスや誤解が生まれます。
そして一度できた思い込みは、疑うことなく信じてしまいやすい。
ここに「思い込みの落とし穴」があるのです。
思い込みをゆるめる4つのコツ
完全になくすことは難しいけれど、「ちょっとゆるめる」だけでも、ミスはずいぶん減らせます。
1. 自信があるときほど、もう一度確認する
「完璧!」と思ったときほど、意外と見落としがあるものです。
2. メモやチェックリストを活用する
目に見える形で残すことで、記憶に頼らずに済みます。
3. 他人の視点を借りる
誰かに「これで大丈夫かな?」と聞いてみるだけで、気づけることがあります。
4. 小さな失敗を許す心を持つ
思い込みによる失敗を責めすぎない。そこから学べばOKです。
「思い込みに気づけた自分」を少し褒めてみる
最近は、ミスをしたとき「また思い込んでたな」と気づけるようになってきました。
その瞬間はショックですが、「前より冷静に自分を見られてるかも」と少しだけ誇らしくもあります。
私にとって“思い込み”は、失敗の原因でありながら、自分の思考の癖を教えてくれる先生のような存在。
それに気づけるようになってきたことが、暮らしをちょっとやさしくしてくれている気がしています。